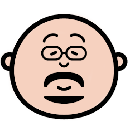いや中継転送機あるやろw
モジュラージャック対応黒電話の頃から使えたのに省庁にある電話は幹線直結の電話なのかよとw
こういう仕組み
A「ガジェットが欲しいのでBさんガジェットをください」
B「売ります」
A「ガジェットの代金をGNU Talerで決済」
A「GNU Taler口座へ国家通貨を送金しコインを受け取ってコインをBに送金します」
B「コインを受け取りました」
B「売上を得るためコインをGNU Taler口座へ送金し国家通貨を得ます」
国家は何故コインが発生したのか?までは監視しておらず、Aが国家通貨とコインを交換したことと、Bがコインを国家通貨に交換したことしか監視していない
実際のところAの保有コインがBに送金されたことまで追跡すると2者間の関係性が監視可能だが、それをしない仕様とすることでプライバシーに配慮するってのがGNU Taler
GNU Talerの場合どうやってプライバシーに配慮しているか?と言えば解決手段が物凄くシンプル
国家が運営するGNU Taler引き出し用口座が存在し、GNU Talerでは国家通貨と等価交換できる兌換仮想通貨の通称「コイン」によって送金を行い、保有コインの量に応じてGNU Taler引き出し用口座から国家通貨を引き出せるという仕組みになっている
つまり、国家はGNU Taler引き出し用口座を介したコインの出入りのみを監視しているだけでありコインによって何が取引されたのかまでは把握しておらず、更にGNU Taler引き出し用口座から犯罪性組織や犯罪性個人を排除することによって不正送金を防ぐという仕組みになっている
市場決済の寡占に至れば通貨偽造を抑制できる上に国家が通貨の移動を監視可能で漏れのない課税、犯罪組織に流れる資金も抑制できるのがメリットで、デメリットは国家に個人の経済活動を監視される上に民間送金業者の成長を阻害する
ちなみに似たような取り組みにフランスが手動した「GNU Taler」がある
https://ja.wikipedia.org/wiki/GNU_Taler
GNUの名が付くようにFLOSSなプロジェクトでこちらは国家が通貨の移動を監視可能でありつつもプライバシーに配慮した設計となっている
ほう?LAMY Safariのような格安国産万年筆として良さげか?
Impress Watch: 2000円で始めるカッコイイ万年筆 パイロット「ライティブ」
https://www.watch.impress.co.jp/docs/series/itsmo/1431466.html
Rollyが肯定的に振り返られている記事をはじめて読んだw
ITmedia NEWS: poiqはソニーのロボット開発の歴史がギュっとつまった逸品だ
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2208/12/news121.html
ライブのアーカイブ観ているけど阿保剛さんの画面に右側にあるにはKORG microKORG
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/49075/
microKORG自体を曲内の音に使うことはあまり無いが、音の傾向の確認などに使うことが多い定番のシンセサイザー
CASIO SA-76、YAMAHA PSS-A50などと同種の用途なのだけれど、より高度な機能を求めた場合にKORG microKORGが選択される
さんすうトレーディングカードゲームを英語で書くとMathematics Tradingcard Gameになって頭文字略称がMTGなのマジで偶然w
まぁ英語の略称はMathTGあたりが解りやすいし違いも明確なるし何なら日本語でもマスティージーって呼んでも良いかも知れん
「さんすうトレーディングカードゲーム(仮)」は本当にイケる気がしてきたぞ
1. 2桁上限の四則計算
2. 戦闘カードは基礎的な1〜99までの基礎的な強さを持つ
3. 戦闘カードは基礎的な強さを1〜99までの四則計算で増減させる特殊スキル効果を持つ
4. 補助カードは戦闘カードの基礎的な強さを1〜99までの四則計算で増減させる効果を持つ
5. 自陣の戦闘ユニットカードの最終的に増減された基礎的な強さが、敵陣の戦闘ユニットカードの最終的に増減された基礎的な強さを上回れば破壊可能
6. プレイヤーはプレイングによる計算結果を宣言し、正答ならばプレイング成功、誤答ならばプレイング失敗となる
7. ゲーム内で使われる四則計算は基本的に小学校算数の難度を超えてはならない(数値インフレによる桁数の超過など例外はある)
8. 除算の余りは切り捨てる
9. ゼロ除算は実装しない
10. 手札の数がプレイングの幅に繋がるのでドローソース系カードの実装は慎重に検討する(ドローソース系のカードは実装しないほうが良いかも知れない)
あとは桁数の違いによる計算難度の変化さえわかればカードの強さをかなり正確に明確化できるなぁ
ただ実際のスムーズなプレイを考えたら1桁、多くても2桁が限界な気がしなくもない
99*99*99の時点で970,299なわけだからプレイしてると2桁上限でも十分にインフレしてしまう
まぁ物凄くインフレするカードは強いけど計算難度が高く、つまりコストが高いのでプレイヤーは簡単に使おうとはしないとは思うけど
【お盆中の水の事故を減らせ!もしも家族が溺れたら】
お盆中、毎年のように悲惨な水の事故が報告されています。
そのため毎年この時期に家族が溺れてしまった際の行動手法の情報提供を行っていますのでチェックしておきましょう。
1. 対象が溺れたからと言って焦り飛び込まない
2. 飛び込まず対象が溺れたポイントから目を離さない
3. 直ぐ大声で周囲へ「家族が溺れている!何か浮くものを下さい!」と何度も伝える
4. 海の場合は118番、川池湖などの場合は119番へ通報しプロからの指示を仰ぐ
協力して貰える人が複数人居るのであれば、溺れたポイントを監視する人、浮きを探す人、通報する人と役割を分担すると冷静に対処しやすいです。
人間は溺れても直ぐには死にません。特に我が子が溺れ苦しそうにすると助けなければと本能的に思って飛び込んでしまいがちですが心をしっかり保って飛び込まないようにしましょう。
誤った行動で飛び込んでしまうと冷静でないアナタ自身も溺れて二次災害へ繋がります。
「飛び込まず118番・119番でプロから指示を仰ぐ」ことが大切な人を守ることに繋がります!
Appleは乗らんだろうiMessegeが囲い込みの1つになってるし
ついに最終回かぁ
IBM PCから41年、そして現在へ PCとは何だったのか、改めて考える https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2208/09/news121.html
- WakazoVLOG - Youtubeチャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UCdM6QZCwyKYmEDjOeM7XC1Q
- WakaGeeks - BLOG
- http://www3.coara.or.jp/~keizou_w/
- Hubzilla
- https://plus.haruk.in/channel/keizou
- Libre.fm(音楽系SNS)
- https://libre.fm/user/keizou