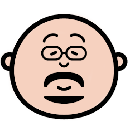東京本社と豊田本社どっちが立場が上なの?と思われるかも知れないけど、どうやらどっちが上というのは無いっぽい
が、色んなところでロビー活動みたいなのするのは東京本社の方なので、政治力が東京本社へ偏ってるから実質的に立場が上なの東京本社だと思われる
伝統と実績は豊田本社の方にあるので組合は豊田本社のほうが強い
これらの問題で最大の懸念が市町村合併や再開発、区画整理により新たな地名が名付けられ継承されてきた地名の意味が失われることがあることです
古い地名を知るには国土地理院の過去の地図を調べるか、郷土資料館などで災害の記録を調べるしかありません
特に郷土資料館は有用で、国土地理院でも把握してない非公式の地名、地元での呼び名が記録されていることがあるので興味があれば郷土資料館を訪れてみると良いかも知れません
ちなみに山間部の付近に蛇、龍、牛などの地名が付き、斜面の地肌が露出している傾向のある地域は古来より土砂崩れや地すべりが頻発していた地域である可能性があります
これは斜面の地すべり痕がまるで化物大蛇が通ったように見えることから名付けられている可能性があり、近代まで忌避されていたものの現代へ入り意味が忘れ去られていることもあります
同様に川や池の傍に龍や蛇と名付けられている地域は水の氾濫が起き、水龍が通ったように見えたから名付けられた可能性があります
このような地域の付近には龍神信仰が根付くことがままあり、付近の神社で龍神が祀られていることもよくあります
ただ水の事故が頻発する地域は現代感覚でも地名がわかりやすくなっている場合もあり、それが淵や渕などの名付けです
死の淵という言い回しがあるように地面と水辺の境界線は足が滑りやすく、そのような地域には淵や渕と名付けられることがよくあります
同様に山でも淵や渕と名付けられていると、その地域は崩れやすいことを意味します
山から滲み出ている水が増えてたり、山の傍の用水路などの水が濁るようになった、普段は乾いたままの雨水を流す用水路へ常に水が流れているようになっていたらまずいです
地すべりや土砂崩れは山の地下水脈が上段と下段を分離することで起きるので、晴れていても染み出す水の量がいつもより増えるような兆候が現れやすいです
木の根は地肌しか山の斜面を保持しないので、木の根が到達するよりも下層が分離すると木があっても地すべりは起きるのです
【定番ソリューション】
・QNAPなどキットタイプNASでバックアップ
【最安ソリューション】
・Raspberry Pi + Nextcloudでバックアップ
パッと作ったけどこうすんねん
たいていアウトラインはプレーンテキストか、HTMLか、ドキュメント形式で出力できるので、それらを編集できるアプリで最後は整形する
例示したものはパッとやったので凄くシンプルだけど、引用資料やらリンクやら画像やらを貼り付けて情報を俯瞰できるようにすると記事作成で便利に使えるぞ
- WakazoVLOG - Youtubeチャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UCdM6QZCwyKYmEDjOeM7XC1Q
- WakaGeeks - BLOG
- http://www3.coara.or.jp/~keizou_w/
- Hubzilla
- https://plus.haruk.in/channel/keizou
- Libre.fm(音楽系SNS)
- https://libre.fm/user/keizou