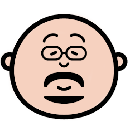これは「メディア」の実体は何なのか?という思考実験にも繋がると思う
先程の例を踏襲するとメディアA•Bはバイナリレベルで同一のものなのでメディアA=メディアBと判定でき、メディアAの保存に違法性があるのならばメディアBの保存にも違法性があって然るべきだろう
ではバイナリレベルで比較するとメディアA≠メディアBだった場合はどうなるのだろうか
バイナリレベルで違うものであるのならばメディアAの保存に違法性があるからと言ってメディアBの保存は即座に違法性があるとは言えなくなる
しかし、もしこの場合でも保存に違法性があるのならば「メディア」の実体はバイナリにはなく、その作風や概念的な部分に「メディア」の実体は宿っているということになる
つまり一度でもメディアAの保存に違法性を認識したら、バイナリレベルで違うメディアBだろうがメディアCだろうが違法は違法という解釈ができてしまう
当然ながら「メディア」の実体は作風や概念的な部分にあるので保存形態によらずキャッシュだろうがなんだろうが保存したら違法である
「京」と来たら「庵」だろ(KOF脳)
ポスト「京」の名称を募集します | 理化学研究所 計算科学研究センター(R-Ccs) https://www.r-ccs.riken.jp/naming
違法アップロードと知りながらコピーしたらダメってことはGoogle画像検索とかTwitterメディアタブとか死ぬんじゃなかろうか
「キャッシュはコピーじゃない」って言うならバイナリを可逆符号で変換したものをキャッシュと言い張ろうと思うw
例の広報手法でプロ作家自身の視点で個人的に驚きなのはココ
> 知らなかったのですが、元々ああいう形式のツイートはアマチュア創作漫画から生まれてきたという文脈があるようです。
すべてのネットミームを把握するのは無理だというのは理解できるけれども、自身が所属するTwitter界隈で爆発的に広まったネットミームを知らないのは「Twitterやっていて何で気付かなかったんだ?非常に難しくないか?」という素直かつ純粋な疑問が浮かぶ
これでは「アマチュアが編み出した広報手法にプロの私はフリーライドしました」と宣言しているようにしか見えなくてあまり良い言説ではないと思う(そういう気持ちがあって書いたわけではないというのは理解してる)
売上が伸びたことはボクも両手を挙げて称賛したいけれど言い回しが雑で危険な気がする
漫画家が第一話を全部ツイートして宣伝したら売上が上がった話|森もり子|note https://note.mu/mori_moriko_/n/n7559ac090b3d
昨日、挙げたロシア系漫画違法ダウンロードサイトのように海外系漫画違法ダウンロードサイトをいくつも知ってはいるのだけれど、それをどのように報告したら良いのか?というのが現状の仕組みじゃわからないよね
いや正確に言えば仕組み自体はないわけじゃない。ただその仕組みを使うと掲載されている作品の権利者(=この場合は作者や管理の委託契約を結んでいる出版社になるだろう)へ逐一報告するという手法を取らざる得ない
これの煩わしさは想像に難しくなく、しかもボクが挙げたロシア系漫画違法ダウンロードサイトは同人作品まで掲載されている。個人に可能なタスク量ではない
フィンランド系とかベネズエラ系とか日本でもチェックできている人が少ないだろう漫画違法ダウンロードサイトデータベースが活かせないのは何とも口惜しい感じはする
これはこれで面白い
ロシアの若者は『ゴールデンカムイ』を見て「北方領土移住」を夢見ている(クーリエ・ジャポン) - Yahoo!ニュース https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190213-00000002-courrier-eurp
[保育所の入所はAIが決める 数秒で選考可能に]
さいたま市は保育園などに入園する手続きにAI=人工知能を活用し、保護者への通知を早めたり、職員の負担を軽減したりする方針です。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20190212/k10011811581000.html
- WakazoVLOG - Youtubeチャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UCdM6QZCwyKYmEDjOeM7XC1Q
- WakaGeeks - BLOG
- http://www3.coara.or.jp/~keizou_w/
- Hubzilla
- https://plus.haruk.in/channel/keizou
- Libre.fm(音楽系SNS)
- https://libre.fm/user/keizou