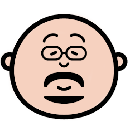更に言えば音楽理論を腹持ちさせることで、人間の単なる模倣ではない新たなコード進行などを探索できる可能性がある
例えば現在の西洋音楽で主流の五度圏パラダイムの音楽だけではなく、例えばJazzのツーファイブワンやThe BeatlsのHey Judeのアウトロで採用されている4度上行進行をカバーする四度圏パラダイムへ知識として持っていない人がアクセスするヒントを得られる
これは現在の音楽生成AIで主流のSunoなどで「どの様にプロンプトを与えればそれができるのか?」はわかりにくいがSDD方式であればAIが提案してきたりするし、J-POPなど日本のポピュラー音楽がJazzの進行を借用する際にAIが明確に「これは四度圏パラダイムであると」明示してくれるようになる
コード進行やメロディ生成について、それを行ってくれるVSTプラグインなども存在するがランダムで出てくるみたいな感じであり、ボクが今やってることはAIと相談しながらコード進行やメロディ生成できる
今やってること作曲用AGENT.mdは「音楽版Vibe Codingだ」なんて言ったけれども、この作曲用AGENT.md開発を進めていると本当にそんな感じになってきたので、作曲用AGENT.md開発のアーキテクチャ自体も現在主流のVibe Codingのアーキテクチャに寄せて「仕様駆動開発(Specification-driven development/SDD)」方式を取ることにした
まぁつまり、SDD方式で主流のやり方であるspecディレクトリ配下に音楽理論に関するディレクトリや各音楽ジャンルのテンプレートに関するディレクトリ、各年代の音楽トレンドに関するディレクトリ...等々を配置して、ユーザの指示・要望に合わせてAIがそれを読みに行くっていう形だ
この方式の良いところは、ユーザが独自にspec配下の関連ファイルを更新することによってユーザの好みに合わせられ、ローカル生成AIでも最新情報を反映したり、ネットには情報が少ないが特定のジャンルに特化した専門家の知識を反映できること
これどうやって進めているかと言えば、ボクは幼少期から音楽をやっておらず肌感覚として「音の表情」みたいなのが感じられない人で、音楽もやる人として育った環境が電気工作から派生して据え置きゲーム機やガラケーやPCでの打ち込み、そのために音楽を理論として捉える傾向が非常に顕著という特徴がある
そのために自身が知る音楽理論やDTM打ち込みテクニックを片っ端からGeminiへ送信し、その中で音楽理論やDTM打ち込みテクニックに関してGeminiとの対話から知識の不足部分を洗い出し、不足部分している部分をGemini DeepResearchへ掛けてレポート論文化を行って、そのレポート論文を再びGeminiへ渡してAGENT.mdに載せられるように要約したり、実際に音を鳴らして情報の取捨選択と情報密度の調整を行ってる
この辺りでボクの強みはプログラム処理のことをよく理解している点で、純粋な音楽家では浅くなってしまうコンピュータ上の処理に関しても作曲用AGENT.mdへ載せられること
いくら突いてもウンともスンとも言わず無言で粛々と沖縄対応を進める石破政権が終わると見るやいなやコレ
やっぱり沖縄対応は無言で粛々とやるの正解なのかも知れん
https://www.sankei.com/article/20251008-PBYS5RATVZMQHIY5UTNOZSJXII/
父「漁師の息子が食い物を残すだとぉ!?オイコラ舐めてんのかぁ!?我が家は他人様に食い物を獲ってくる事でメシ食ってんだよ!!残すなぁ!!全部食ええぇぇ!!!!」
という教育を受けて育ったため、お残しは許されないというのが魂にまで刻まれてしまっており、食い尽くすというか残さず食べているだけです
まぁでもボクの血筋はどうやら大食いらしくて、姉貴たちも「友達の女の子が全然食べなくてビックリした」と学生当時言っていた
ヨメさんも最初はボクの食事量に驚いていたが今は慣れたようでボクが満足する量を見極めて出してくる
まぁ自分でも何かしら1曲やってみようかね
- WakazoVLOG - Youtubeチャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UCdM6QZCwyKYmEDjOeM7XC1Q
- WakaGeeks - BLOG
- http://www3.coara.or.jp/~keizou_w/
- Hubzilla
- https://plus.haruk.in/channel/keizou
- Libre.fm(音楽系SNS)
- https://libre.fm/user/keizou