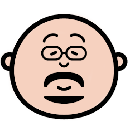なぜNATOとの協調戦略だと有効なのか?だけど、まぁつまりロシア軍の兵站が機能不全に陥ってる最中にNATOの大軍が援軍として来るため
ロシア軍からするとNATOの大軍がウクライナ領土に入らずポーランド-ウクライナの国境で待機しているだけで相当な圧力になる
NATOが身構えているのでロシアは対NATOのために物資を前線へ送らないといけないし、ウクライナ領土内に駐屯するロシア軍は対NATOのために物資の消費を抑える必要がある
しかし、ウクライナが羽虫のようにアッチコッチとロシア軍兵站を執拗に刺してくるので計画通りの兵站運用が出来なくなり、結果としてウクライナ領土内に駐屯するロシア軍は攻勢を抑える必要が出てくる
NATO協調戦略パターンだと、ロシア軍は物凄いストレスに晒されるのでプーチンがかなり饒舌になると思うよ
最近インフラの破壊にシフトしつつあるのは不味い傾向な気がしてならない
いや、ロシアがウクライナ領土の実効支配地域を増やしつつある現状、ウクライナ領土内に駐屯するロシア軍もまた多く必要で、その増えたロシア軍を維持する為の物量もまた増加するので、ロシア国内インフラの攻撃目標的価値が上昇しているというのは理解している
ただ、これまでのウクライナ軍はロシア軍が攻めれば出血が増えるという専守防衛的なドクトリンを重視していて、ロシア国内への攻撃も専守防衛的なドクトリンを活かすためのものだった
つまり、ウクライナはこれまで徹底的に"人(兵)"を狙うドクトリンだったのだけれど、最近は"物(特にインフラ)"を狙う傾向が強くなっている
何らかの理由で従来のドクトリンから新しいドクトリンへ移行しなきゃいけなくなってるんじゃないか
「これがNATO軍との協調戦略です」って言うなら物凄く有効な動きだとは思うけどね
コロナ禍から言ってるけど、ハードウェアの重要性がポートフォリオの大半を占める会社ではリモートワークは絶対に無理
そりゃAppleも新社屋を建てますわと
スタイルだけ真似てフルレンジ一発で誤魔化すみたいなことせず2WAYにしたのはコスト掛かってる感あってイイっすね
追加するURLにも依るけれどレベル79を超えた時点で大学受験数学は余裕のクリア
これの応用とちょっとの調整で基礎教科をすべて行えるんじゃなかろうか
ただ、図標問題の生成が安定しないので、例えば作図とか化学や生物、歴史など画像がいっぱい出てくるのはまだ改良の余地ある
シンプルなベン図とかは生成できることは確認済みなのだけれど、高度な演算が必要な3次元グラフとかは安定しないんですよね(演算途中にタイムオーバーした上での結果が生成される)
大学受験のためのAIによる学習法の活用案を作ってみた。
https://g.co/gemini/share/8271143595dc
参考にする学習サイトURLを追加するとより良い感じに問題を作ってくれるはず。
なお、アホみたいに高い偏差値97.89は大学受験の最高理論値なので気にしなくて良く、レベル100になるとバケモノの領域として設定してるだけw
これでディスプレイサイズへ合わせて表示・非表示を設定できるんだけど、もしかして各ディスプレイに合わせて各々の設定をしなきゃダメなんだろうか?
「dpiが横いくつ以上ならどうのこうの」とプログラマブルな設定はできない???
もしWYSIWYGで出来ないならばDart(Fluutter記述言語)で書いたほうがマジで早いんだが
ノーコードツール使ってるデザイナーさんはマジでこんな面倒くさいことを1つ1つやってるのか???
ていうかブランド創業初期に電波遮断でめちゃくちゃ叩かれた過去があり、その悪評に心折れず改善を重ねてリリースし続けて悪評を覆した
Xperia向けもずっとリリースし続けるなど国産アルミバンパーメーカーとしての地位を確立した
iPhone Airのバンパーはアルマニアさんが頑張りそうではある
それぞれの要素毎のサイコロを振らせるねん
完治する確率のサイコロ、副作用Aが出る確率のサイコロ、副作用Bが出る確率のサイコロなどなど
これらのサイコロを同時に振って、サイコロを振る回数を重ねることで、その治療法がどれくらい有効か?を体感できる
例えば、完治するけど副作用で結構辛い想いをしやすいとか体感できるようになる
- WakazoVLOG - Youtubeチャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UCdM6QZCwyKYmEDjOeM7XC1Q
- WakaGeeks - BLOG
- http://www3.coara.or.jp/~keizou_w/
- Hubzilla
- https://plus.haruk.in/channel/keizou
- Libre.fm(音楽系SNS)
- https://libre.fm/user/keizou