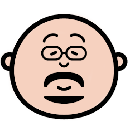画像はAndroid端末のアクセスパーミッションコントロールだけれど、こういったUIがパーソナルコンピュータに来たことは注目すべきことなんじゃないかと思う
Linuxはその特性上、実験的な試みとして(時には過激な)先進機能を採用することがあり、その試みは他のパーソナルコンピュータOSに影響することがある
直近ではmacOS Mojaveで採用されたダークモードは、UNIX/Linux向けデスクトップ環境のGNOMEでグローバルダークテーマとしてmac OSよりも先じて採用されたという実績がある(グローバルダークテーマの着想はmac OSで増えていたアプリケーション独自のダークモードに影響されたもの)
もし今回のSnapの試みの評判が高ければ、Mac Appストア経由でインストールするmac OSのMacアプリや、Microsoftストア経由でインストールするWindows OSのUWPアプリで採用される可能性がある
A guide to snap permissions and interfaces https://insights.ubuntu.com/2018/11/01/a-guide-to-snap-permissions-and-interfaces/
CanonicalがUbuntu blog上で次世代パッケージ管理システム「Snap」でのアプリケーションアクセスパーミッションコントロール(アクセス権限制御)の解説をしている。
誤解を恐れず言えば、SnapではiOSやAndroid OSのようなアプリケーションアクセスパーミッションコントロールを採用し、よりセキュアなアプリケーションの利用が可能になっている。
これまでパーソナルコンピュータ向けのアクセスパーミッションコントロールでは、アクセスできるディレクトリ(フォルダ)を管理者が包括的に制御するのが通常であり、特に周辺ハードウェア機器のアクセスコントロールは特別な操作が必要だった。
SnapではスイッチングUIの採用によって特別な操作のユーザビリティを高めている。
情報提供として今回の「Apple Special Event. October 30, 2018」と今までのApple Special Eventの変化をギーク的な視点で気付いた1つの事をご紹介します。
今回のApple Special Eventの配信はAppleドメインでは行われませんでした。
配信を担当したのは米国企業のアカマイ・テクノロジーズ社です。
アカマイ・テクノロジーズ社は世界有数のCDN企業であり、顧客にはAppleのほかIBM、Microsoft、Google、米国防総省など巨大な組織。
これまでAppleドメインで行われていた配信ですが、今年からHD解像度になりました。
おそらくは今年数度のAppleが行ったイベント配信に於いてAppleドメイン配信では手にあまることが表面化し、安全性を考慮しアカマイ・テクノロジーズドメインでの配信に切り替えたものと思われます。
Appleドメインで配信された過去のイベントでの配信もおそらくは何処かのCDN企業が受託していたものと思われますが、今回ははっきりとアカマイ・テクノロジーズ社が関わっていることが判明しました。
すっかり忘れていた
Apple Special Event.October 30, 2018. Livestream URL
https://p-events-delivery.akamaized.net/1810hbasdviuhbadsvouhibnascvokjn/m3u8/hls_mvp.m3u8
Webブラウザなどを介さなくてもVLC Media Playerなどで視聴できます
ドリキンさんのサンフランシスコ動画でよく見るSMSによる待機通知
日本でも流行るんじゃないかな?なんて思って色々考えていたけれど、店側にAndroid端末1台さえあれば直ぐにでも実行できそうな感触を得てる
もちろん新たにAndroidアプリを作っても良いのだけれど、SMS操作に対応しているAndroid上でCLI環境を構築できる「Termux」や「Linux CLI Launcher」などを使えばイケる
ただしお客様用の電話番号入力UIは何らかの方法で準備する必要はある(これもAndroid端末だけで完結できる)
問題があるとしたらお客様の携帯電話番号は個人情報なので、店頭に置くAndroid端末に覗き見防止フィルムを用いたり、SMS送信後に個人情報は保存しないようにしたほうが無難であるということ
Webページデザイン評論は沢山読んだことあっても、Webページ構造評論はココのところあまり読んだことがないなぁ
構造の話になるとJavascriptとかバックエンドの話になってHTMLを主体とした構造の話はされなくなっていると思う
インターネット黎明期のWebページはマシン性能やソフトウェア技術の拙さもあり、表現幅が非常に狭かった
現代では比較すること自体が馬鹿らしいレベルの差があるけど、次々と登場する新技術に追いつくために忙しくなり、根本的な「綺麗なHTMLを出力する」という部分が軽視されているように思う
もちろん作り手側の様々な意見も理解しているけれど、今一度ボクは「綺麗なHTMLを出力する」に眼を向けて欲しいなと感じる
ついさっき気付いていなかったけれどTwitterまとめサービスのTogetterの仕様がいつのまにか変わってる
これまでのTogetterはまとめられたページへアクセスすると、すべてのツイートを読み込み、Javascriptで表示画面を圧縮し「続きを読む」ボタンで展開する方式だった
しかし現在の仕様は「続きを読む」ボタンをクリックしないとツイートが読み込まれない仕様へ変更されている
仕様変更後の利点としては、初回読み込みのデータ量を抑えることが可能で、見掛け上はそこそこ高速にWebページが表示されることや、クローラボットなどによるWebスクレイピングを防ぎ、Twitter情報の3次4次利用によってTogetterというサービスの価値を維持することが出来る点が挙げられる
欠点としては様々なWebブラウザへの親和性は従来の方式が高いことであり、具体的には技術的に視覚障害者向けの読み上げWebブラウザなどはJavascriptを解しにくいので、諸事情によりJavascript対応の低いWebブラウザユーザは離れてしまうという点がある
リーナスの影響なのかGNUプロジェクトに人と人のコミュニケーションに関わるガイドラインが発表されたw
GNU Kind Communications Guidelines
https://www.gnu.org/philosophy/kind-communication.html
> People are sometimes discouraged from participating in GNU development because of certain patterns of communication that strike them as unfriendly, unwelcoming, rejecting, or harsh.
>人々は非友好的で、不快で、拒絶的で、更に過酷な交流方法が存在することで、GNU開発への参加を避けてしまう開発者がいる。
どこのコミュニティのことを言ってるのか丸わかりであるw
- WakazoVLOG - Youtubeチャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UCdM6QZCwyKYmEDjOeM7XC1Q
- WakaGeeks - BLOG
- http://www3.coara.or.jp/~keizou_w/
- Hubzilla
- https://plus.haruk.in/channel/keizou
- Libre.fm(音楽系SNS)
- https://libre.fm/user/keizou