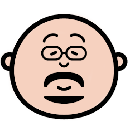このロケーション、現地知ってる人が見たらメッチャ笑うと思うんだよなw
パッと見でカッコイイ感じになってるじゃないですか?
白飛びしている部分の左の壁、実はココに男子トイレの入り口がありますw
つまりココはトイレへ向かうための通路ですw
Seijiさんが共有した動画で天井バウンスの3灯目が真正面から来ているように見えるのはコレをやってないから
おそらく偶然だと推測してるのはこのため
照明を使ったほうが撮影的に有利だと理解をしているけれど、照明の基礎基本があやふやなまま運用したので偶然に面白い影になったんじゃないかと
意図的にやったらもう少しハッキリとした多重の影になると思う、いや断言は出来ないけどね
3灯ですね
1灯は部屋を明るくするために天井バウンス、2灯はほぼ正面の少し高い所から左右で照射
つまり正面の2灯はT字型スタンドで照射してます
更に言えばこの2灯どうやら光量に差をつけているみたいです
この影が面白いと思ってやったのか機材上の制限による偶然なのか意図はちょっと読めないですね
ハレーションをコントロールする気も無いみたいですし偶然で面白い影ができたのかも?
まぁマネージャーになるとシチュエーションによってはこんなもんだろうで人月計算使うけどね
単に書類へそういう数字が載らないだけで
違いは空間を感じるロケーションを選択できるかどうか、別に撮影の上手い下手じゃない
ボクの手癖で日の丸構図でも空間表現入れちゃってるけど2枚目のほうが空間を広く感じられ、そのために踊り手の動きがダイナミックに見えやすい
更に言えば1枚目は別アングルを考えた際は非常に別アングルが難しく、この画角・アングルで背景が完成されてしまっているため別アングルにすると背景の完成された美しさが破綻する
2枚目は空間の情報が豊かで別アングルにした場合、2枚目から1枚目と背景が変化したとしても視聴者は「銅像の方へ移動したんだ」と2枚目の情報から推測できる
動画は時間的変化をする媒体なので視聴者が目にする1発目でそれとなく次の上方へ繋がるヒントを入れておくと非常に後から使いやすくなる
- WakazoVLOG - Youtubeチャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UCdM6QZCwyKYmEDjOeM7XC1Q
- WakaGeeks - BLOG
- http://www3.coara.or.jp/~keizou_w/
- Hubzilla
- https://plus.haruk.in/channel/keizou
- Libre.fm(音楽系SNS)
- https://libre.fm/user/keizou