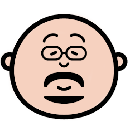まぁぶっちゃけ普通にYAMAHAが安い
YAMAHAライクな真面目すぎる鳴りなので低音ドコドコ鳴らしたいみたいなのにはまったく向かないくて人を選ぶけど
YAMAHAは綺麗に鳴らしすぎてプロ評論家から一般消費者に至るまで「いや良いんだけど物足りない」ってレビューが散見するw
今気付いた
「センスの良い言葉選び」で「AIへ指示するセンスの良いパラメータ選び」を察して欲しかったけどちょっと難解だったかな?
一般大衆に「AIへ指示するセンスの良いパラメータ選び」する能力や知識など無いと言いたかったんだけど
そして絵師は依頼人にセンスが無いことを察して補完してあげるのが腕でしょと
では教育が普及した現代で代書屋は需要がなくなり消えたのか?と言えばそうではありません
前述した通り代書屋とは詩人であり、売れていた代書屋は詩人と呼ばれるようになって一般大衆の識字率が向上した世の中で一般大衆へ向けて詩集を出版するようになったのです
ではセンスの良い言葉選びが出来なかった売れない代書屋はどうなったか?と言えば、彼らは彼らで公的文書の作成の仕事が残っていたので現代日本で言うところの「行政書士」と呼ばれている
つまり代書屋という言葉が使われなくなっただけで過去の代書屋は現代で詩人もしくは行政書士と呼ばれているのです
多くの絵師は依頼人からの依頼に応じて絵師の博学を活かしたセンスの良い作品を納品するという仕事でしょうから似たような結果に収束するとボクは予想してます
文字を知っていても代書屋の博学とセンスはついてきません
「AIの教師データへ既存のイラストを使うと絵師の仕事が奪われる」という主張は「一般大衆に教育や道具を与えると我々の仕事が奪われる」と非常に親しい主張なんですよね、隣接・近似していると言って良い
例えば過去の時代に「代書屋(代筆業)」という商売がありました
日本では1600年代に導入が開始された現在の檀家制度の影響によって登場した寺子屋で文字が教えられ識字率が急上昇したため例外的ではあるけれど、代書屋が広く社会へ普及し歴史ある欧州へ目を向けると、代書屋の中には明らかに売れる代書屋と売れない代書屋が存在しました
代書屋は手紙や公的文書の代書をすることで生計を立てる商売なわけですが、依頼者の意志を反映するだけの代書屋の売上になぜ差が出るのか?と言えば欧州の代書屋という存在は詩人とほぼ同義だったからです
代書屋には博学が求められ、歴史学や文学、神学など幅広い知識によって依頼者の依頼内容に合わせてセンスの良い言葉選びをする代書屋が売れた
この能力は特に恋文へ需要があり、過去の欧州人はそうやって関係性を深めていったわけです
絵師さんには前にボクが解説した「AIは何を出力してるか理解してない」っていう部分を肌感覚で良いから知って貰いたいなぁと思うね
AIは1 + 1 = 2という計算結果を出力できるんだけど、AIはこの2が何を意味するのか理解できないんですよ
もしかしたら人数かも知れないですし、買い物のお釣りかも知れません
我々人間は計算をするとき2が意味するものなんて余裕で解釈できるわけですが、というか意味を求めて2を計算結果を出すわけですがAIにはそれがない
絵師は意味を求めて絵を描くが、AIは意味を求めて絵を描きません
絵師が用いる鉛筆やペン、筆は画材道具なので鉛筆やペン、筆自身は何を描いているか理解していないはずです、画材道具に意志が宿らない限りはね
一部の方々はもうお気づきでしょう、画材道具に意志が宿るという未来を想定、もはやそれはSFの世界です、物語の領域です
SFは大変面白く興味深いですが、AIが意志を持たない道具超えると想定し始めると仕事が奪われるとかそういうレベルの話ではなくなり、今回のイラストレーション生成AIの問題の範疇を越える
絵師の不安感はそこにはないはずです
炭酸コーヒーは毎回騙される
「アレほど不味いって言われてるのにまた出したんか!!!」
「・・・いや待てよ?もしかしてついに改良されたのか?」
「はは・・・そんなはずは・・・モノは試しだな」グビグビ
「不味いじゃねーか!!!!!」
おそらくAIへ不信感を感じているイラストレーターはデジタルイラストレーションを知らなかった水彩画の柴崎先生みたいなものだと思ってますね
柴崎先生はすぐにデジタルを画材として便利さへ適応しましたけれど、AIを画材と考えられるかがキモなのではないかと
グルドンには刻田先生もいらっしゃるし、イラストレーターがAIへどう適応していくと将来的に良さげなのかご意見伺いたいですねぇ
この前の静岡旅行はGoToトラベルクーポンと言う名の静岡県内限定地域振興券を使いましたよ
息子のお金の使い方を勉強するのに活用した
お釣りが出ないので面倒くさくない
- WakazoVLOG - Youtubeチャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UCdM6QZCwyKYmEDjOeM7XC1Q
- WakaGeeks - BLOG
- http://www3.coara.or.jp/~keizou_w/
- Hubzilla
- https://plus.haruk.in/channel/keizou
- Libre.fm(音楽系SNS)
- https://libre.fm/user/keizou