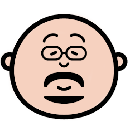@martialalchemy そうですね、ソフトの進化はすごいと思います。iPhoneで曲作れてしまいますから…
魅力的なハード、という意味だと、コルグのKRONOSのようなソフトウェアシンセ+ハードと、volcaシリーズのような触るのが楽しいシンセの2つの路線になる気がしてます。
クラフトワークはVAIOでライブするんですか!?音楽系は盲目的にMac使う文化があるものだと思ってたので意外でした。Cubaseもライブ向きではなさそうですけどねー…。
@osanpo ほぉー、1万超えてくるんですね…確かにvolcaのつまみの方がPOシリーズの電子工作みたいなボタン(失礼)より触ってて楽しそうです。
POもVOLCAも単機能故にいっぱい揃えたくなりそうでまだ手を出してません笑
@yojimuraD 小学生の頃にねだってカスタムモデル買わせた親不孝ものです…
ローランドとかクラヴィアから出てた足鍵盤、高いですよね。今も出てるのかな?
D-DECKは後継モデルが去年あたり出てましたよね。エレクトーンは(良くも悪くも)1人で完結してしまうのが悲しいところかなと思います
ドリ散歩 #192を見ての感想
ドリ散歩ってよりは、すっかりオッサンポみたいなやられっぷりですね
ご自愛ください
でも腰痛ネタがあるあるネタだったみたいで、動画が大人気ですね。
YouTuberもとい腰痛berとして第一人者になれるかも?
動画ですが前回も気になったのですが、GoProが謎のフレーム落ちするようになってませんか?
GoProの突然死の前兆みたいで怖いです。
あと23:42付近でドリキンさんはスルーしてましたが、撮影車?みたいな車いましたね
でかいカメラが付いてませんでした?
https://mstdn.guru/media/iKWLbyn19R9dj8bCoYk
@mazzo 高度経済成長が一段落したものの、心の豊かさやゆとりのある生活を求める人が多くなった1970年代。音色・機能を一段と充実させたエレクトーンは広く一般家庭に普及していきました。
'70年には小学生を対象にした「エレクトーンスクール」が開設され、'71年には「月刊エレクトーン」が創刊。'72年には初めてオートリズムを内蔵したD-3Rが発売されました。
また、技術の粋を結集したシアターモデルが次々と開発されたのも70年代のこと。
大阪万博が開催された'70年にはEX-42が、沖縄海洋博が開催された'75年にはポリフォニック・マルチシンセサイザーともいうべきGX-1が登場。
電子楽器の常識を遥かに超えたGX-1は、スティーヴィー・ワンダーやキース・エマーソンも愛用する“ドリームマシン”でした。
そして、'77年に発売されたD-60、D-90、EX-1には、パルス(デジタル)、アナログ、シンセサイザーの技術を融合させたPASSystemが導入され、楽器としてのクオリティは一段と高まっていきます。 こんなのが、まだ現役で動くんですよhttps://mstdn.guru/media/0v6pOJxq8DEbbG7TVnY
音楽ネタとか拾ってくつもりです